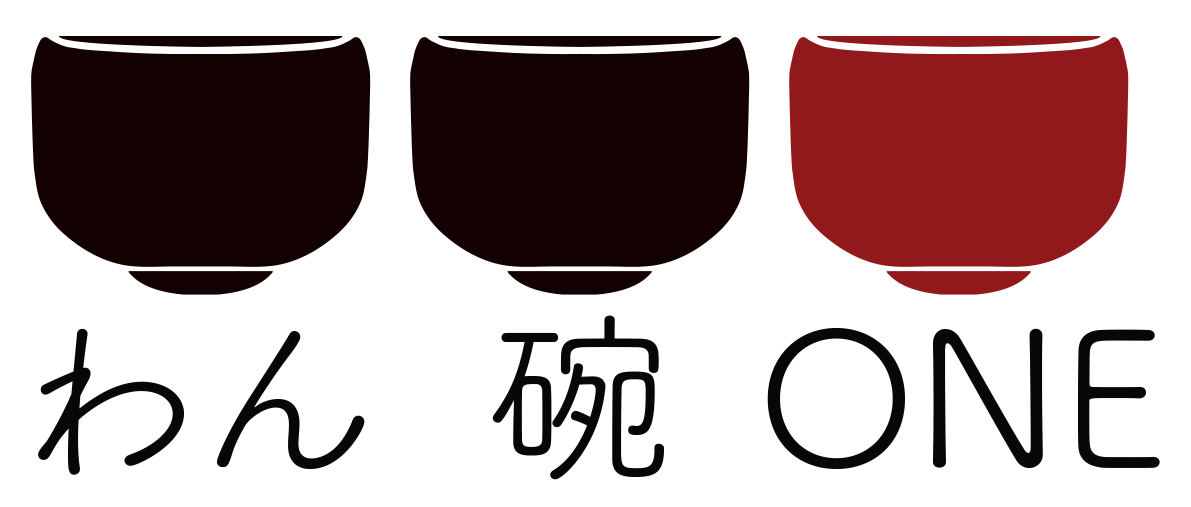Your cart is empty Continue Shopping
「京都やきものWeekわん・碗・ONE」
へようこそ!
このイベントは、京都が誇る伝統文化、京焼・清水焼の深い歴史と魅力を皆様にお伝えするために誕生しました。
一つの作品が持つ京焼・清水焼独特の多様性とその表現の豊かさを、心ゆくまでご堪能ください。
へようこそ!
このイベントは、京都が誇る伝統文化、京焼・清水焼の深い歴史と魅力を皆様にお伝えするために誕生しました。
一つの作品が持つ京焼・清水焼独特の多様性とその表現の豊かさを、心ゆくまでご堪能ください。
「わん碗ONE展」— 現代京焼作家の「今」
中ノ堂一信

茶碗の原点は8世紀の中国唐時代に作られていた青磁茶碗、白磁茶碗などにある。中国で喫茶の習慣が全国的に広がった時期とも一致する。その頃の茶碗の形状は平碗系、すなわち口縁部が外に開く端反り型の形状をしており、以来中国の茶碗(唐物茶碗)はこの平碗系を宋時代の天目茶碗、明時代の染付茶碗、色絵茶碗,色釉茶碗でも継承してきた。また、その傾向は朝鮮半島で作られた茶碗(高麗物茶碗)の高麗青磁茶碗、井戸茶碗、三島茶碗、刷毛目茶碗などにも反映されている。
これに対し安土桃山時代に日本で作られ始めたのが胴部分を垂直に立ち上がらせた筒型の形状の茶碗であった。美濃地方の黄瀬戸茶碗、瀬戸黒茶碗などにその作例がある。また京都で千利休の好みとして誕生した楽茶碗も筒型を基本として、高台から腰は手取りの良い碗形の形状を見せる半筒型の形状の茶碗が制作された。この筒型や半筒型の茶碗は従来の唐物茶碗、高麗物茶碗にはまったくなかった新規の茶碗であった。


<形>を主眼に茶碗の歩みを見てきたが、この度の「わん碗ONE展」でも平碗系、筒型系、半筒型系などの形状をもった茶碗や盃がそれぞれ独自の色彩美、模様美を発揮して出品されている。しかも個々の出品作品を通観すると白磁、青磁、鉄釉、天目、鈞窯、染付、色絵、金彩、銀彩、井戸、刷毛目、御本手、楽、白釉陶、青釉陶などの実に多彩な陶技釉法が駆使されたものをみることが出来る。その作風の多彩さ、そしてそのなかで共通する洗練された造形センス、色絵の文様などのみやびな印象はさすがに京都ならではの陶芸の展観という感想を抱く。新型コロナウイルス感染拡大という未曽有の時期下ではあるが、100人余の陶芸家の作品を一堂に集めた今回の展示によって、私たちはコロナ禍にあっても意欲に満ちた作陶を続け、明日への希望に繋げていく現代京焼作家の今日的状況を知ることができることと思う。